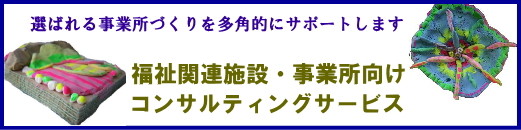ひとりひとりの『生きがい』『生きやすさ』をサポートする団体です

NPO法人 健やかネットワークは2001年6月、「小地域」を意識した活動をスタートしました。
これまで「心の健康」等の講座開催、サロンの開所などを通じ、小地域福祉文化の醸成に努めてきました。
これからも一歩一歩前進してまいりますので、活動へのご理解、ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
*ささきのささやき*

◆真夏の夜の夢 ◆
7月の梅雨明け前でしたが、熱帯夜の真夜中の出来事!!
遅くても寝るのは9時過ぎですので熟睡中の12時前、玄関のチャイムが鳴りました、
いや鳴ったような気が。夢かな、寝ぼけたかとボーっとしていると再度チャイム!
間違いなく我が家であることを確信するがどうしたものか暫し思案。
奥さんの知り合いが多いので一先ずドアミラーで確認するも人影なし、恐る恐るドアを開けると通路を歩くご婦人が居ました。
「チャイム鳴らしましたか?」と声をかけると無言で近づいて来られる、緊張の一瞬です。
「どちら様でしょう?」に、にっかり。「お名前は?」に、「○×」・・・・
「このマンションにお住まい!」に、にこにこして首を振られます。
これは素人での対応は無理と判断し、警察に通報。恰幅の良い警官が登場するまで、お茶をさしあげ、椅子に座ってもらいました。幸いスマホを持っておられたので警官がご主人と連絡がとれ、そんなに時間が掛からずご主人が登場で大事に至らず一件落着。
何れはわが身の第2弾です。正に「真夏の夜の夢」、ちゃんちゃん!!!
2024年文月

◆『ぼくの哲学』考 ◆
わたしは入院中に何冊かの本を読んだ。このうちの一冊がアンディ・ウォーホル著『ぼくの哲学』である。アンディは1929年生まれ、1960年グラフィックデザイナーとして展覧会に出展し脚光を浴び、その後自主映画の製作、出版、TVコマーシャル出演など一躍有名人となった。そして40代になってこれまでの自分を振り返る意味で1975年にこの本を出版。
わたしはアンディを知らないので、ある意味先入観なしで楽しく読めた。
自己紹介的なことから始まり「愛」「美」「時」など全部で16タイトルからなっている、
子どもみたいなところがあると思うとニヒリズムが混在し、ユーモアが心を擽る。
中でもわたしの目に留まったのは当然ながら「死」である。内容はと言えばたったの2行
「ぼくは死ぬということを信じていない、起こった時にはいないからわからないからだ。
死ぬ準備なんかしていないから何もいえない。」
アンディが40代半ばで感じる死生観は余りにも淡白。それから12年後の1987年入院中の病院の過失により急死する58歳である。この簡潔な言い回しは突然の死を予言したように感じるのはわたしひとりだろうか?!?
誰にでも必ず訪れる「死」ではあるが80代になって、周りが急にざわざわしてきた。時には仲間と静かに語り合いたいテーマの一つになったことは間違いない。
2024年文月

◆「足指じゃんけん」の効用◆
「内容が個人に関わることであり投稿を躊躇しましたが多くの方にご心配とご迷惑をおかけしましたので生還のご挨拶として掲載をお願いしました」
敷地内のさくらがほぼ満開、ケヤキも芽吹き春の輝きに満ちています。その賑わいも入院日を除き曇天で楽しませてくれまない、患者の心境には相応しいといえます。
1月の終わりからわたしを悩ませている前立腺肥大症を思い切って手術することにしました。スケールの小さいわたしの前立腺が人さまより大きいのだそうです、我が家の長男も前立腺がんでしたので遺伝かもしれません。
手術当日も予想通りの曇り空、12時から開始予定が遅れに遅れ14時半スタート。事前に主治医から「92歳の方でも問題なく行える病気です、ただしあなたのは大きいから3,4時間かな」と告げられていたので手術時間が長いのは致し方ないとして、全身麻酔であることに不安いっぱい。
4時間後、ざわざわした中で目覚めました。自分がどこにいて何をされたかも定かでありませんでしたが、何人かの「無事終わりましたよ」で覚醒。
自室に戻って家族に逢えてからが大変、「足が重い重い!!」を連発しまくる。手術前に血栓予防ソックスを付けていたのでなおさらです、イメージはサイボーグの下半身で、大げさに言えば地面に引き込まれる感触。
看護師さんがフットポンプという機器を付けてくれて少し改善。自分でもなでたりさすったりを試みるも効果なし。ダメもとで高齢者向けの「足指じゃんけん」にトライ。これが大当たり。少し話す気持ちになれたのには驚きです。
高齢者のみなさん「足指じゃんけん」がこんな場面で役立つとは嘘のような本当の話でした。
2024年卯月

◆日本は『消齢化社会』だそうだ!!◆
この言葉を聞いた人は少ないだろう。今年の8月に博報堂生活総合研究所が30年に及ぶ膨大なデータから読み取った我が国の実像を新書として発行した。
ここでは「消齢化社会」を大まかに20歳から69歳までの生活者の意識や好み・価値観などについて、年齢による違いが小さくなる現象が進む社会と定義している。
その一番の理由をバブルがはじけて以降、低成長が続いて、所謂失われた30年を共に過ごした世代だとしていることは納得できる。
後期高齢者世代と消齢化世代(こんな括りが出来るとして)との歴然とした世代間格差(ギャップ)は多様であり、そこから生じる社会課題の解消は一筋縄ではいかない。
そのことは2025年問題が話題にもならず風化しつつある現状を見れば明らかである。
人生100年時代、ただ死に行くだけにしては道のりは長い。同研究所の知見から「共生社会」確立の道筋が導き出されるのか興味のあるところである。
2023年長月

◆非認知的能力がヒトと地域を救う◆
コロナ禍の長期化で高齢者の認知機能低下が次第に明らかになる。確かに外出や人との接触が制限される中で、高齢者が自ら選んで対処できる項目は限定されていると言わざるを得ないのだから、まさに追いつめられていると言っても過言ではないだろう。
更なる長期化は子どもから高齢者までさまざまなダメージを受けることが懸念される。
そんな中、子どもの教育に関連してこれまでの認知的能力偏重から非認知的能力を伸ばすことの重要性を指摘する本に出合った。
機能は物のはたらきであり、能力は物事を成し遂げることのできる力であると大雑把に定義すれば、二つの語彙の間に大差なしと考える時、子ども教育に非認知的能力の視点が大切ならば、高齢者にとってもこの視座は人生100年時代が囁かれる今、大いなる突破口になるのではないだろうか!
確かに認知機能は歳の経過とともに低下することは明らかだが、これまでのわたしの高齢者との関わりの中で、コミュニケーションや協働といった人間関係に関わる非認知機能は年齢の関係なく個人差が顕著と多くの場面で見受けられる。
認知・非認知機能、双方が車の両輪としてその役割を果たせれば、例え認知症を発症しても豊かな高齢期を過ごすことが可能ではないだろうか!
この文脈に着目してこれまでの認知機能維持重視から非認知機能を高める啓発と実践活動を行っていきたい。
これが2021年度弊NPOのミッションの一つになりえると確信している。
2021年花つ月

電話による安否確認及び困りごと相談
「安心もしもしサポート」
1 サービス開始:2021年2月1日
2 利用料金:下記料金は目安です。利用者様のご相談に応じます。
・毎日:1500円
・隔日:800円
・週1回:400円
3 お支払方法:月単位でスタート時に前払い
・集金に伺います。(ほかにご希望があればご相談に応じます)
4 申し込み先:佐々木(090-9843-9430 又は03-3976-4908) 今後数人加わる予定
5 サービス利用の流れ:
●事前打合せ&サービス内容説明(原則面談、電話やメールでも可)
⇒申込用紙記入
[①住所 ②お名前 ③受信する電話番号 ④受信希望時間 ⑤利用料の決定 ⑥個人情報保護の約束 ⑦緊急連絡先 ⑧安否確認の電話の担当者のご希望:指名( )/誰でもよい/女性希望/男性を希望 から選択
⇒サービスの決定と利用料金の授受⇒サービス開始
6 その他:①通話時間は原則5分以内です
②利用記録を報告します
③情報や資料を希望する場合は送料・コピー代の実費を別途ご請求します
急募・妄想(もうそう)仲間募集します!!

ご興味のある方はご連絡ください!
妄想(もうそう)仲間募集します!
@閉塞感がいっぱいの地域社会に元気がない
@市民の社会参加・参画・貢献が浸透しない
@寄付文化が育たない などなど
これらの社会課題の解決には従来の思考・手法ではイノベーション(変革)ができない。固定概念に捉われない、自由で想像を超えた非真面目な発想が必要と考えております!
*こんな方どうぞ!
@自称・妄想家と思う方
@自分は子どもの時から「とっぴなことを考える子」みたいに言われたことがある
@今、自由に使えるお金がもらえるのは嬉しい(これでは困るのですが…)
ご注意(下記の2点をご留意の上、ご応募ください)
@その提案が公序良俗に反するものでないこと
@国内外の先行事例や知見の発見提示を求めるものではないこと
*変革の源泉は心身がフリーな時に宿ると考えての提案です
@かって、炭鉱には「スカブラ」(平時にはブラブラしているが事故やトラブルの時に、駆け付ける人たちのこと)がいた
@勤勉と言われているアリの中にも働かないアリがいる
@以前グーグルには「20%ルール」制度「従業員は勤務時間の20%を自分のやりたいプロジェクトに費やさなくてはならない」があった
募集要項
●募集人数:概ね5名
●報酬:1人5万円
●活動内容:妄想仲間として様々な妄想をご提示いただきます
●活動期間:半年間(双方合意の上、延長有)
●応募方法:原稿用紙1枚程度(例:わたしの妄想度など)
メール又は郵送(連絡先・お名前をお願いします)
●応募締切:2021年4月30日(金)(必着)
●合格発表:2021年5月21日(金)
●応募者が未成年の場合は保護者の同意が必須です。
(応募の際にその旨を記載願います)
●その提案が可能性ありと判断したものは弊団体の活動の一つとして活用します
妄想が沸いたら…
宛先 特定非営利活動法人健やかネットワーク
住所 〒175-0094 東京都板橋区成増2-37-2-509
TEL/FAX 03-3976-4908メール rei_ma@h4.dion.ne.jp
①お名前 ②ご連絡先(メールアドレス、および電話番号)
を明記ください。
※この企画は『妄想する頭 思考する手』歴本純一著 祥伝社刊行を読んでヒントを得ました!!ご関心のある方はぜひご一読ください、但し読むことが応募要件ではありませんので念のため・・・
イベント情報

そろそろ・ぼちぼち
親の介護を考える連続講座[前期]
2013年に、約2カ月余をかけて開催した10回連続講座
そろそろ ぼちぼち 親の介護
略して「そろぼち講座」を
2019年も開催いたします!
お申し込みは、
メール rei_ma@h4.dion.ne.jp
または
FAX 03-3976-4908
①お名前 ②ご連絡先(メールアドレス、および電話番号) ③参加人数
を明記ください。
※下記にカリキュラムを掲載しています。
カリキュラムと開催時間 (いずれも土曜日の開催になります)
第1回 4月6日 10~12時
「多世代の視点から地域共生社会を考える」
東京都健康長寿医療センター研究所 野中 久美子さん
第2回 4月6日 13~15時
「運動をはじめる・つづけるコツを学ぶ」
東京都健康長寿医療センター研究所 根本 裕太さん
第3回 4月13日 10~12時
「高齢者の社会参加効果は‘’三方よし‘’」
東京都健康長寿医療センター研究所 藤原 佳典さん
第4回 4月13日 13~15時
「中高年期のワークライフバランスとは」
東京都健康長寿医療センター研究所 小林 江里香さん
第5回 6月29日 10~12時
「高齢者のストレスと心身の健康」
東京都健康長寿医療センター研究所 小川 将さん
第6回 6月29日 13~15時
「改めて助けられ上手のススメ」
東京都健康長寿医療センター研究所 村山 幸子さん
会場:東京都健康長寿医療センター研究所 多目的室
(板橋区栄町35-2)
募集人数:30名
参加費:無料(応募多数の場合は抽選且つ全回参加者を優先)
その他:第7~第12回の[後期]は9月以降開催予定
主催:NPO法人健やかネットワーク
協賛:東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム
後援:いたばしコミュニティスペース連絡会
南蔵院こども会~「聞き書き」にチャレンジしてみよう!!~

みなさんはおじいちゃんやおばあちゃんとゆっくり話したことがありますか?
(一社)日本家政学会第3回家政学夏季セミナーにて登壇いたしました
(一社)日本家政学会第3回家政学夏季セミナーに、当法人理事の佐々木が登壇しました。(開催日:平成30年9月6日)
公開シンポジウム
テーマ:生活の質的向上を目指す家政学の世界 -子どもの貧困と子ども食堂-
上記セミナーで発表した内容が、日本家政学会誌に論文にまとめられて発表されました
「あい×あい」で地域包括ケアの実践を 活動報告
1月26・28・31日の三回にわたり学び合いを実施。
参加者は45名と少なかったですが、多様な方々の参加で一定の手応えを感じました。
引き続き「地域包括ケア」「地域共生社会」をキーワードに実践の学びを継続します。
今後は厚労省が打ち出した「我が事・丸るごと地域共生社会」は3層協議体をイメージしたものと捉え、仮称「わがまるネット」をスタートします。情報の集約・共有や「助けて!シート」作成など緩やかに活動予定です。
今回の『「あい×あい」で地域包括ケアの実践を』のレジメ希望の方はご連絡ください
・第1回浅川さん 第2回東京都 第3回板橋区 各5部
・要送料120円
・申し込み先
rei_ma@h4.dion.ne.jp
新講座:住民主体の新しい総合事業の実践
ご存知の方、教えてください
以下の内容についてご教示いただける方を探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。
研究テーマ:仮題「地方行政改革の一視点」
問題の所在
地方分権・地方創生(地域創生が適切)が叫ばれて久しいが市区町村(以下行政という)の組織には大きな変化は所見されない。我々地域住民が感じる行政像は下記の様に集約される。
1:縦割り組織で行政内部に縄張り意識が強く、事業遂行に組織内での横断的な発想がない
2:何よりも安定性を重要な意思決定基準としている為新しい発想(視点)を受け入れない
3:数年単位で人事異動がある為専門知識の継続や長期的視点での判断が困難となっている
4:地域課題の多様化・複雑化・重層化は行政だけでは限界のあることを理解していない
5:「協働」「連携」が形だけのものになっており形作り傾向は否定できない
6:職員は真面目であるが住民との接触にアレルギー感が強く且つチヤレンジ意識が希薄
研究の視点
指摘した点の多くは施策の決定・遂行プロセスに欠陥があることに起因するとの認識に立ち
下記に述べる改革を行うことにより流れが変わり大きな変革が起こると考えられる。
其々の行政予算に占める国・都道府県からの助成金・補助金(助成金等という)は可なりの部分を占めている。ということは独自事業は僅かということでもある。これらの助成金等が行政内部で如何に検討され施策に組み込まれたが住民に明らかにされていない、もっといえばこんな事業に助成されていることも積極的に開示しない。問題点は下記のようにまとめられる。
1:各種助成等事業を積極的に住民に開示しない
2:各種助成等事業を行政施策に取り入れるか否かを行政内担当箇所で決定する権利はない
3:各種助成等事業を行政施策に取り入れたとしてもモデル事業と称し随契により秘密裏に行うことがあり加えてそれを積極的に開示しない
改革に視点
これらの問題点を考察する時、端的にいえば決定プロセスに最大の欠陥があることを指摘し
下記の提言を行いたい。
1:全ての各種助成等事業を行政の仮称「助成等事業総括室(略称総括室)」が一括管理する
2:この総括室のヘッドはこの考え方に共感する者を行政内部から募る
3:この総括室は下記シンクタンクが業務の中核を担う、更に強力な事務局を置く
・構成員:都道府県・市区町村など全ての行政OB及び専門的知識を有する住民更に高い関心のある住民。
・人選等:自薦・他薦により公平に行い、任期につては今後検討する
・機密保持:知り得た情報の機密保持の為の誓約書を提出する
・報酬:原則なし、通勤及び業務上の交通費は支払う
4:総括室の業務のイメージ
・全ての各種助成等事業を検討・研究精査するとともに行政内で実施の各種政策・計画等との整合性を検証する
5:総括室は年数回単位で報告書にまとめ議会に提案する
6:議会から前向きな検討の承認を受けた後、住民にこれら事業を開示、説明会(担当部署も
参加を義務化)を実施し参画を検討する事業者・団体等が現れた時点で初めて担当部署に
引き継ぐ
7:この後も総括室は担当部署への情報提供等行いP・D・C・Aに則り当該事業のスムーズな実施をサポートする
8:年度末には仮称「総括室」レポートを作成総括する
期待される効果
1:住民が持っている行政への閉塞感や不信の払拭の手掛かりとなる
2:住民へ情報が確実に伝わる
3:行政職員の意識改革に結びつく
4:議会の機能が大きく変わる
5:住民の行政への参加・参画・貢献革命が起きる など
以上
初回 2007・11・20
改定 2010・10・31
改定 2015・2・25
ボラたま情報
2015年10月から、いたばし総合ボランティアセンターの職員が定期的にたまりば・とうしんに来所してます。(毎月第1・第3水曜日11~12時)。
ボランティアセンターの周知・市民活動の推進・災害時の連携など、ボランタリーな地域拠点を目標にしたいと考えています。
【こんなことができます】
・ボランティアセンターのPR、事業紹介
・ボランティアの依頼、ボランティアが出来る方の相談・申込み
・ボランティア保険加入の手続き
ボランティアに興味がある方、ボランティアをお願いしてみたい方・・・
ボランティアに関する相談を受け付けています。
●毎月第1・第3水曜日11~12時まで どうぞお越しください。
南蔵院でランチ倶楽部へぜひお越しください!

蓮沼町にある桜で有名な「南蔵院」ホールにて、ランチ倶楽部を運営しています。
ランチ倶楽部はみんなで食べて、話して、楽しいひとときを過ごします。
栄養や健康に関するお話なども行います。
ぜひお気軽に、ご参加ください。
〔南蔵院ランチ倶楽部〕
おとしより健康福祉センターの指導のもと、おとしより相談センター・地区民生委員・町会の全面的なバックアップによりスムーズにスタートし、現在では月に3~4回開催しています。
☆ 時間 11時から13時まで
☆ 会場 南蔵院ホール(蓮沼町48-8)
☆ 参加費 1回550円 (体調により弁当持参も可、その時は1回50円)
☆ その他 ・欠席の連絡は開催日前日の正午までに下記へ連絡のこと
注)不定期に終了後「ゴムひも体操」が行われます(1回500円)
注)南蔵院さんの行事により中止になることがあります。
※見学等随時行っていますので前日の12時までに申し込みください。
利用料:利用料:550円 ゴムひも体操500円
お問い合わせ・お申し込み先
NPO法人健やかネットワーク 03-3976-4908
南蔵院こども会の開催スケジュール
平成27年度東京都多様な主体の地域貢献活動による地域包括ケア推進事業が本格始動

南蔵院ランチ倶楽部が仏教タイムスに掲載されました

東新児童館ハロウィンであそぼう応援募集!

昨年も大好評だった東新児童館とのタイアップイベント
『ハロウィンであそぼう』を応援して下さる方を募集しております。
2歳児のかわいいお子さん達が仮装して、たまりば・とうしんに遊びに来てくれます!
時間:10月30日(木)10時30分~11時30分
過去のハロウィンパーティの情報はこちら
新しいサービスをはじめました
健やかネットワークの活動について

人と人とのつながりはもちろん、福祉活動においても活動団体の協働はこれからの時代において、大変重要な要素だと考えております。
健やかネットワークの「ネットワーク」は人と人とのつながりを核として、助け合い・支え合いのつながりを結んでゆくことを使命として活動しております。
NPO等の設立・運営サポート
みなさんのミッションを大切にし、目的達成に向けて側面からサポートいたします。
サロン(小地域のたまり場)やカフェの開設・運営サポート
近い未来、サロンの差別化が重要になると思われます。
参加されるおひとりおひとりのニーズ、地域の特性に応じた活動が求められてくるものと考えております。
個性を大切にしたサロン・カフェを地域は求めています。
福祉関連施設・事業者向け コンサルティングサービス
介護事業業界はますます厳しい時代に!!
◎運営者の熱い想い
◎利用者本位のサービス
この2つで生き抜けるとお考えですか?
私たちは「想い」「共感」「共有」をキーワードに地域で求められる事業所へ・・・
実現可能な提案とそれに向けた実践のサポートを行います。
まずご連絡ください、一日伸ばしが状況の悪化を招くばかりです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地域の介護現場に入り、活動を通して利用者と事業者のコミュニケーションをさらに促し、気づきのシステムをつくり、両者の円滑で良好な関係を実現するための『橋渡し』となり、利用者の満足度、事業者の満足度の双方を上げ、『選ばれる事業者』として生き残り、地域に根づいたサービス展開・運営をサポートいたします。
「助けられ上手」を考える出前講座
対象はすべての住民です。
「自助・共助力」が育たないと社会は持ちません。
気軽に声をかけてください、出前いたします。
福祉・まちおこしなどの地域課題の講座企画・運営サポート
さまざまな地域課題の解決・啓発のために地域住民向けの講座等を企画しませんか?
地域課題の洗い出しから、問題提起、解決への道筋を、いっしょに考えていきましょう。